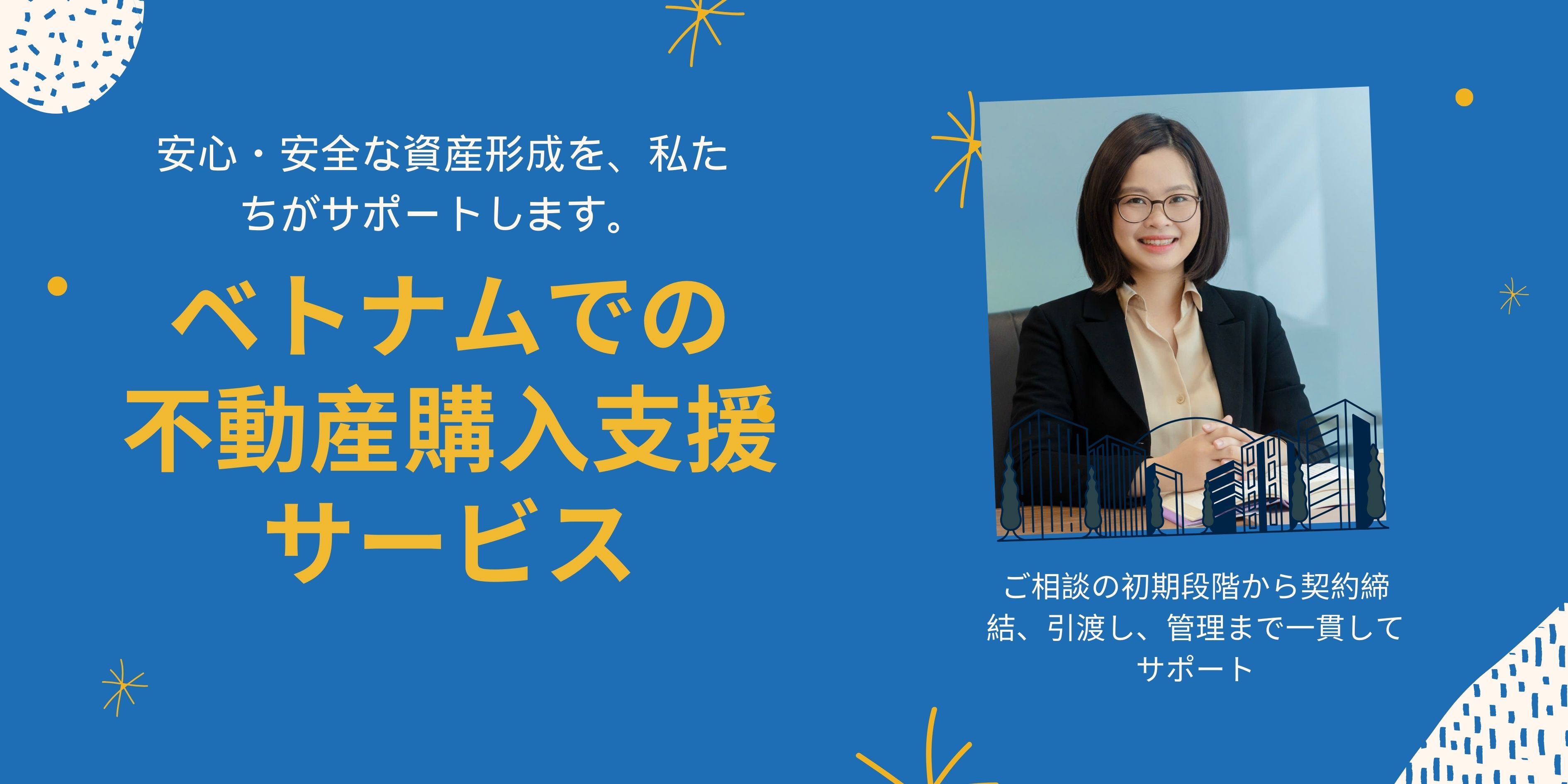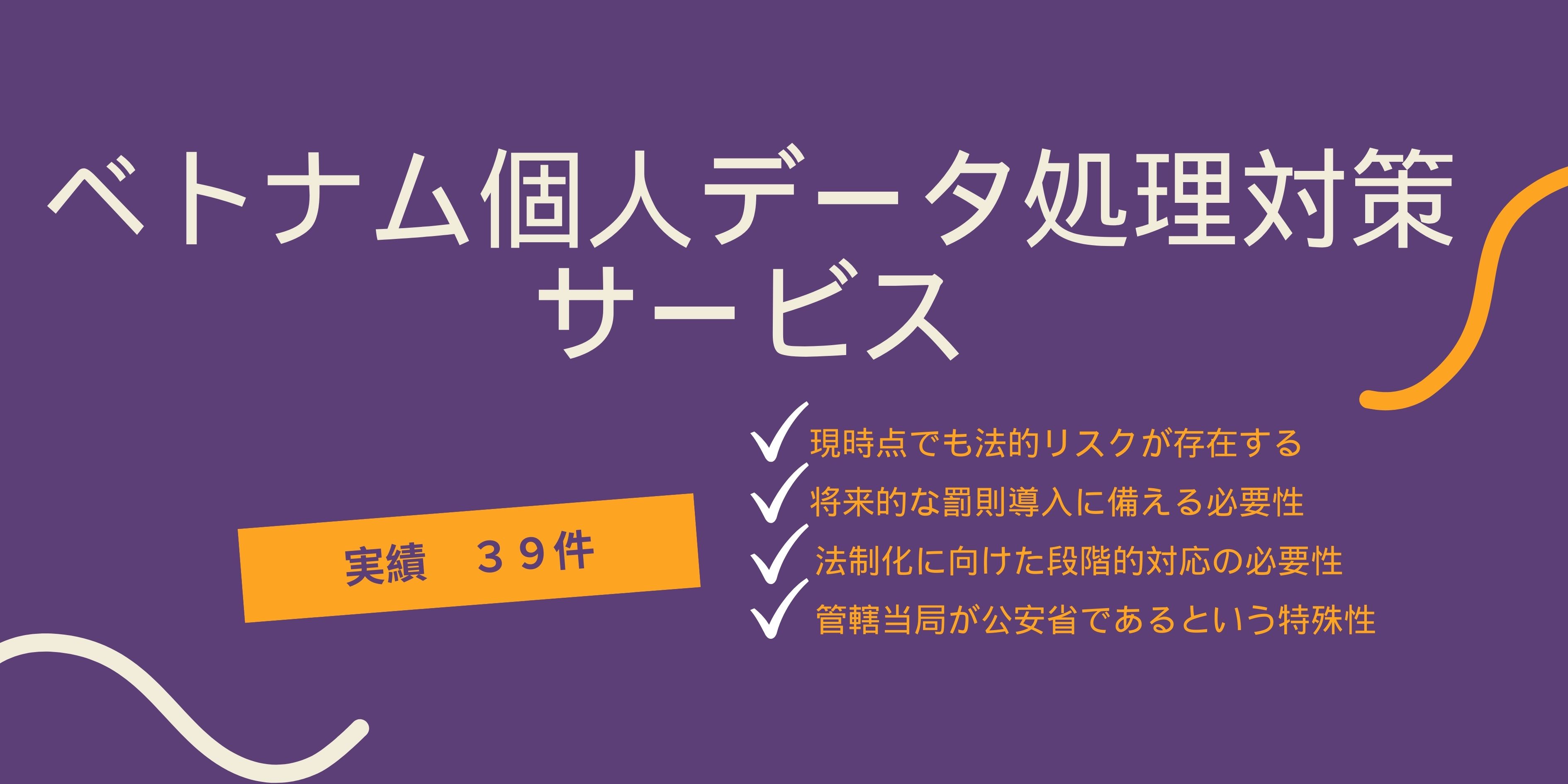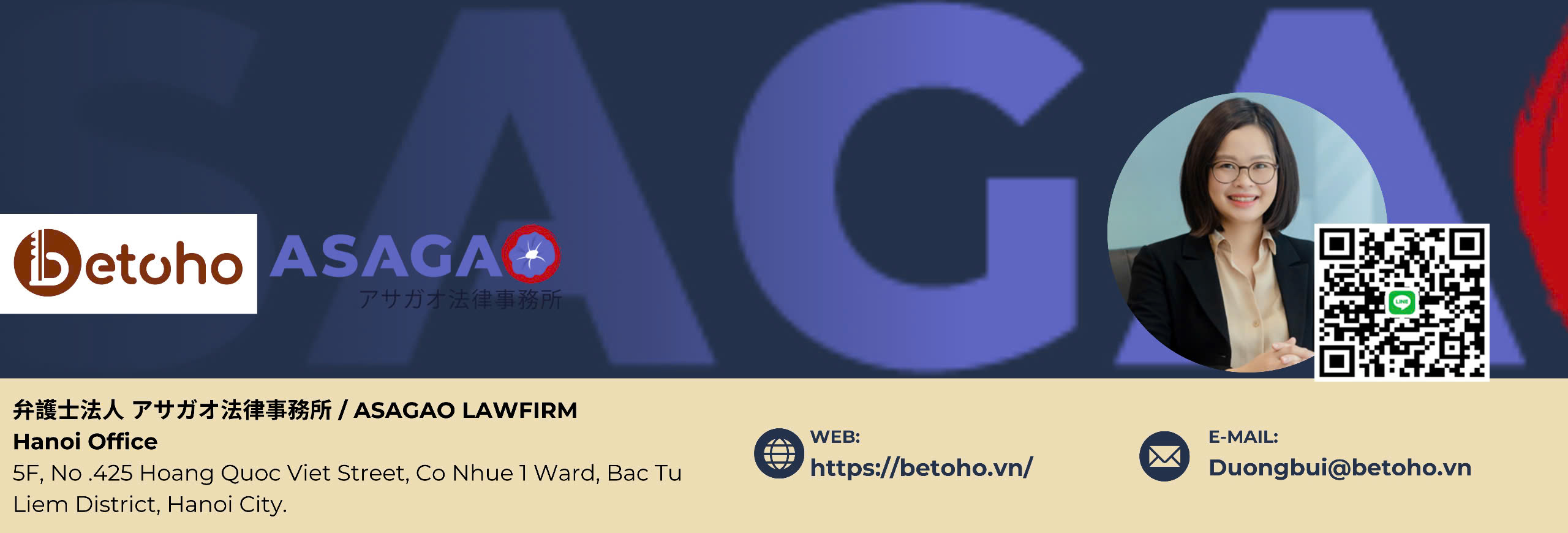|
|
01 - 事案の概要 |
|
XXX社は、ベトナム市場向けに自社ブランド品をオンライン販売するため、公式ブランドサイトを立ち上げ、現地企業であるA社と連携したEC事業(以下「本EC事業」)を検討しております。 本スキームにおいては、以下の特徴があります。
(XXX社はA社に対してブランド品を卸売り(輸出) → A社から顧客さんに小売り) このような事業形態において、外国企業によるオンライン販売、個人情報保護、広告規制、消費者保護等、多方面にわたるベトナム法の影響が想定されます。 |
|
|
02 - ベトナム弁護士による法的助言 |
▶ 法的論点①:輸出入・販売構造と外資規制の整理
- XXX社がA社にブランド品を輸出する行為は、ベトナム商法第16条に基づき外国商人による貿易行為に該当し、ベトナム国内での事業活動には該当しません。そのため、XXX社からA社にブランド品を輸出(卸売り)を行うために、ベトナムでの現地法人を設立する必要がありません。
- A社はローカル企業であり、ブランド品の輸入・販売(卸売り・小売り)を合法的に行うことが可能です。
- ブランド品の区分により、輸入する前に、輸入ライセンスを取得する必要がある可能性があります(例:化粧品の場合は、事前の成分開示手続きを行う必要があります)
- 輸入ライセンスを取得する必要であるブランド品の場合は、輸入者(A社)にて対応する必要があります、その場合、XXX社からA社に対してブランド品に関する情報(書類)を提出する必要があります。それらに秘密情報を含まれる可能性があります。そのため、XXX社とA社との間の秘密保持対策等を検討する必要があります。
▶ 法的論点②:費者保護法(2024年改正)への対応
- 改正消費者権利保護法(2024年7月1日施行)では、外国商人も規制対象者に追加され、XXX社にも一定の責任が生じる可能性があります。
- ECサイト運営者(XXX社)・販売者(A社)は、商品情報、保証条件、苦情窓口、返品ポリシー等をサイト上に明示する義務を負います。
✅提案された対応策:
- サイト内に以下の項目を明示する。
- 商品情報(原産地、価格、配送条件等)
- 保証ポリシー(返品条件・免責事項)
- 問い合わせ先(苦情受付)
- A社との契約において、商品情報の管理・更新義務を明確化しておく。
▶ 法的論点③:XXX社とA社との間の売買契約の構成
個別合意に基づく条文の構成であるため、省略します。
▶ 法的論点④:その他
【ECサイトと広告規制】
- XXX社は、ベトナムでは販売資格がなく、広告主の資格も有しないため、広告内容提供者としての立場にとどまります。
- 広告前には内容の事前届出と審査取得を実施する必要があります。
- 事実的な広告主(XXX社)と形式上の広告主(A社)の関係や、責任分担等に関する整理が必要です。
【個人情報保護政令(No.13/2023/ND-CP)への対応】
- 本事業では、XXX社とA社が個人データ管理者兼処理者に該当します。
- 顧客の個人情報(氏名・電話番号・住所など)を扱うため、以下の重たる対応が求められます。
- 同意取得文書の整備:収集目的、処理内容、同意権撤回方法などの記載を明示(政令第11条)
- 処理影響評価(DPIA)と越境移転影響評価の実施:データ処理開始から60日以内に作成し、保管
- プライバシーポリシーの策定と公開(政令第27条)