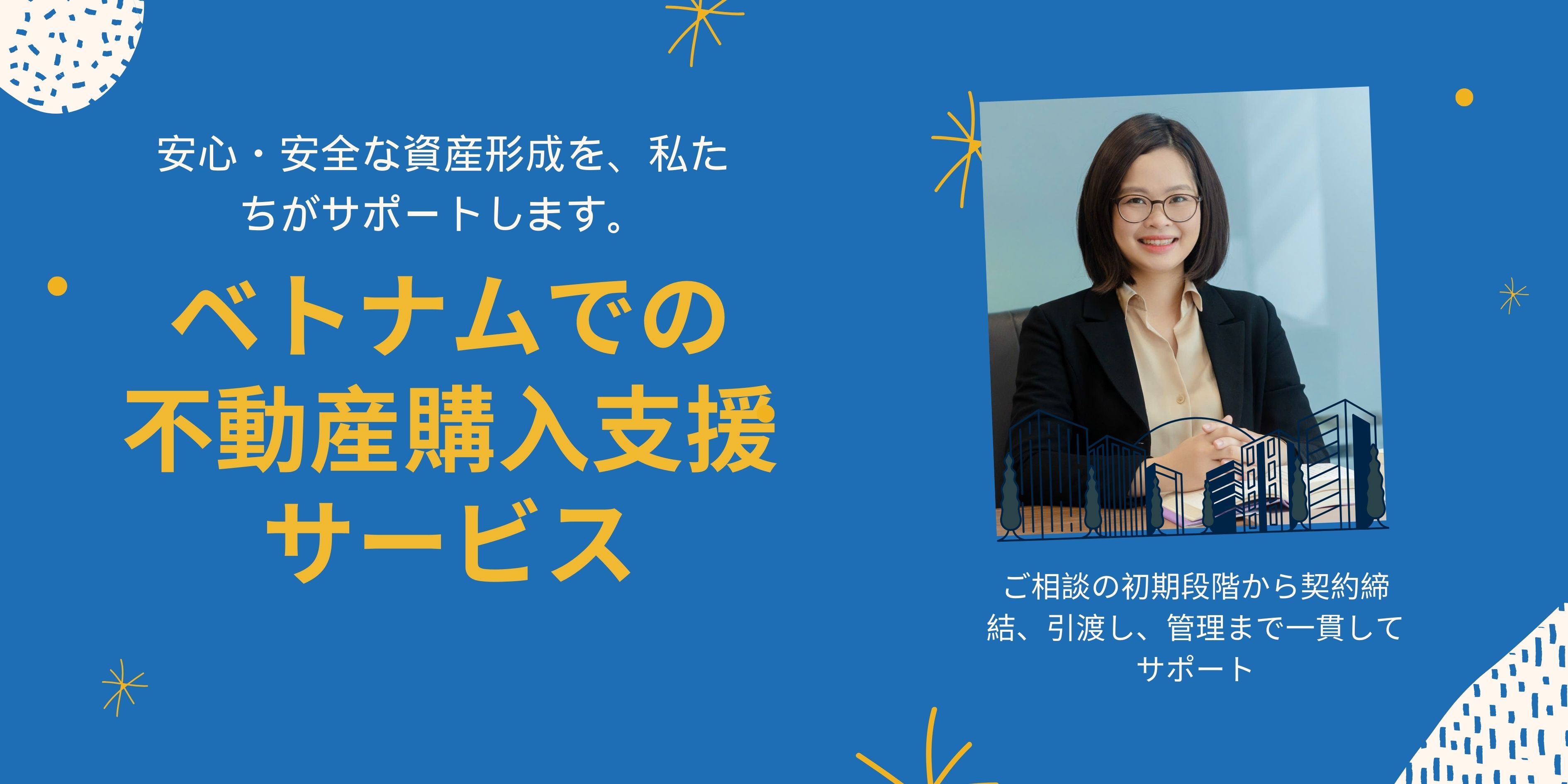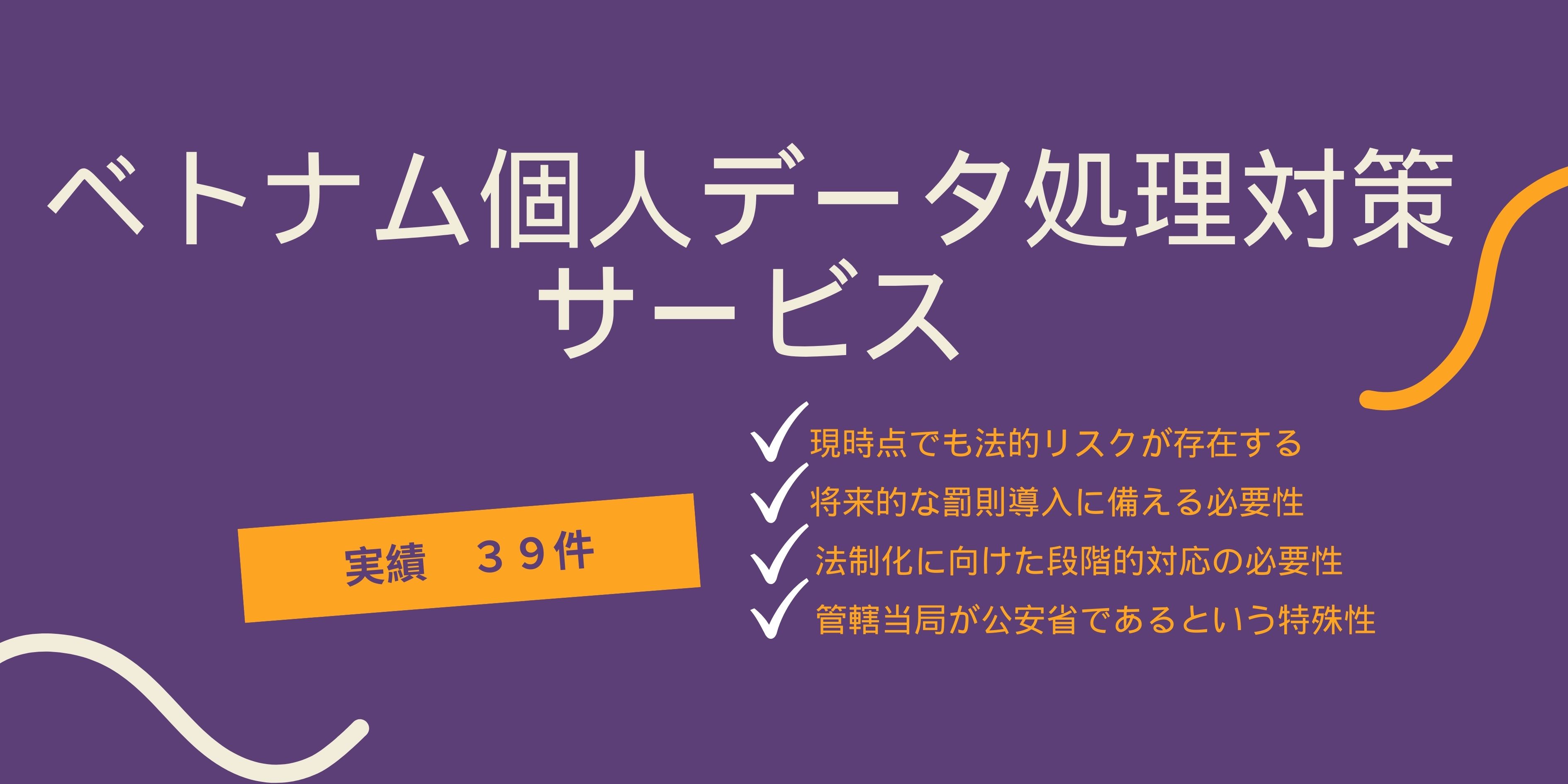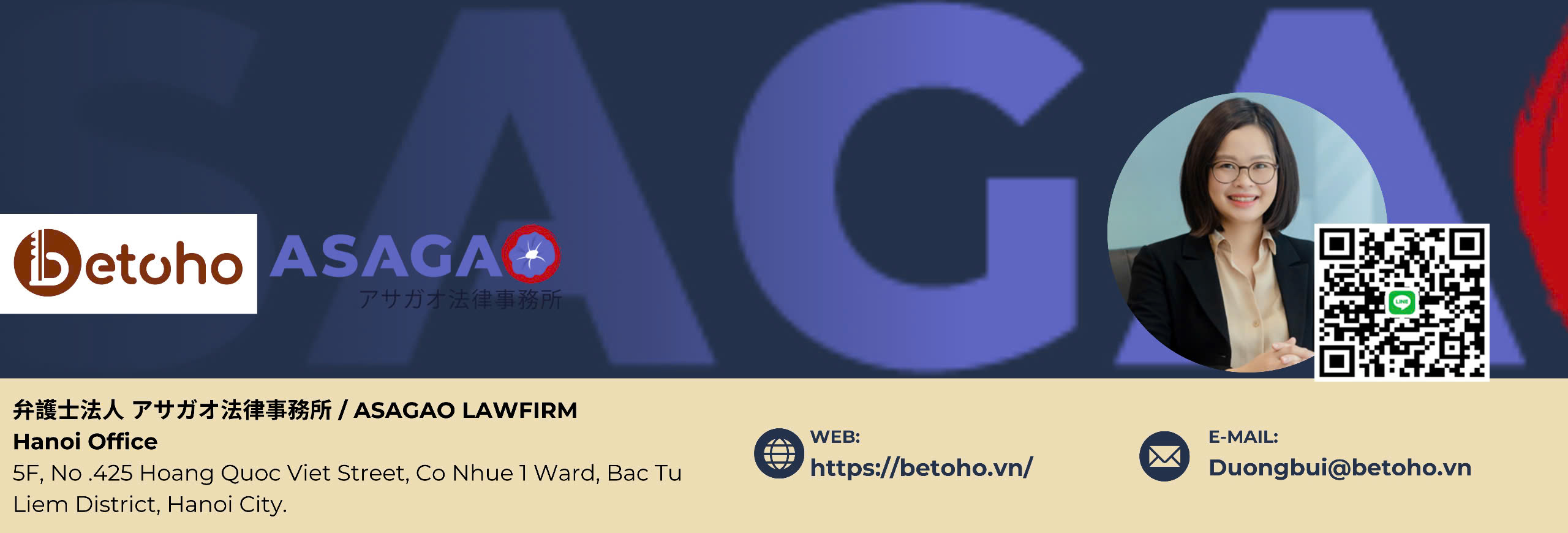|
|
01 - 事案の概要 |
|
XXX社は、日本本社所属の社員を短期的にベトナムへ出張させる機会がありました。これらの社員(以下、「出張者」)は、現地法人との雇用関係を持たず、給与も日本本社から支払われております。 このような形態でベトナムに一時滞在する出張者に対して、ベトナムでの個人所得税(PIT)申告義務が発生するかどうか、また、日越租税条約の適用による免税が可能かどうかについて、XXX社より法的見解を求められました。 |
|
|
02 - ベトナム弁護士による法的助言 |
▶ 法的論点①:出張者は非居住者でも納税義務を負うか?
- ベトナムの政令No.65/2013/ND-CPおよび通達111/TT-BTCによれば、非居住者であっても、ベトナム国内で発生した給与所得に対してPITの申告義務を負うと規定されております。
- 特に、ベトナム国内で業務を行った結果として給与が支払われる場合は、その給与がたとえ外国法人(例:日本の親会社)から支払われたとしても、「ベトナム源泉所得」として課税対象となります。
✅よって、XXX社の出張者がベトナムにて業務を行った場合、その給与のうち当該業務期間に相当する部分については、原則としてベトナムでのPIT申告義務が発生することとなります。
▶ 法的論点②:租税条約による免税の可否と実務運用上の問題点
- 日越租税条約第15条により、以下の条件をすべて満たす場合、出張者の所得はベトナムで免税されます。
① 連続する12ヶ月間に183日未満の滞在
② 現地法人から給与が支払われていない
③ 給与が日本から支払われ、日本側に費用計上されている
- ただし、ベトナムにおいてこの免税制度を実務的に活用するには、申請書類の提出および当局の審査を要する手続きが必要です。
✅必要書類一覧
- 免税申請書
- 日本の住民票(原本または認証写し)
- 雇用契約書(課税関係を証明)
- パスポートのコピー
※ 上記には、領事認証および翻訳公証が必要な文書が含まれる
▶ 加えて、法令上は30日以内の処理が標準とされているものの、実務では処理遅延・制度未認知の問題が多く発生していることが確認されております。
▶ 法的論点③:居住者に該当する可能性とそのリスク
- 滞在日数が183日未満であっても、たとえば183日以上のサービスアパート等の賃貸借契約を締結した場合には、「居住者」と認定されるリスクがあります。
- 特に、法人名義で借りた住宅に出張者が住んでいる場合でも、当局からの確認対象となる可能性があるため、注意が必要です。
✅居住者と認定された場合は、ベトナム国内外を問わず全世界所得が課税対象となり、日本側での調整も煩雑化するリスクがございます。
|
◆結論と今後の対応指針◆ 現在のベトナム税務実務において、出張者であっても一定の納税義務が発生することは避けられず、租税条約を利用した免税申請は実務的な負担・不確実性が高いという状況にあります。 ✅XXX社への具体的な提案
|