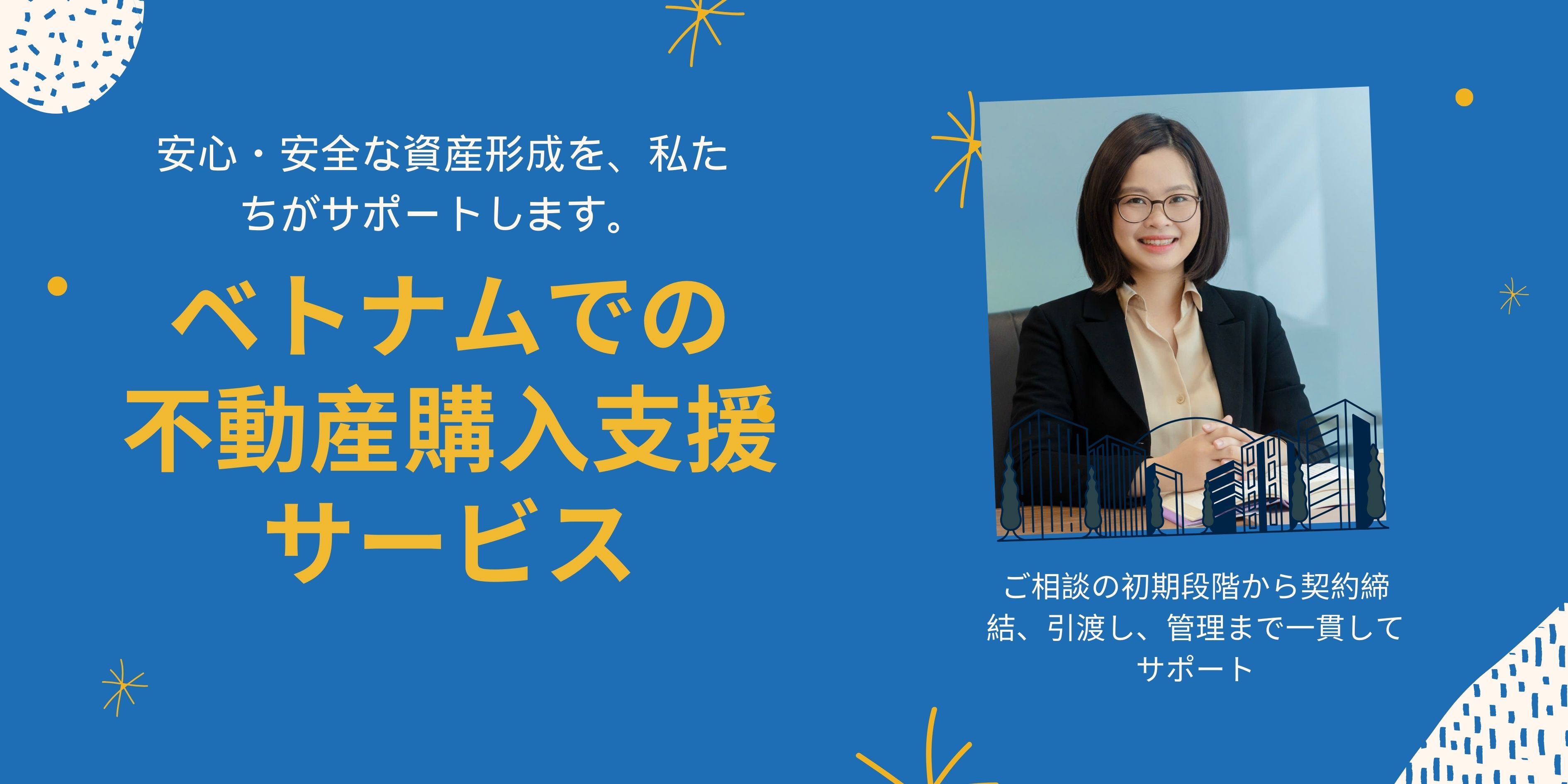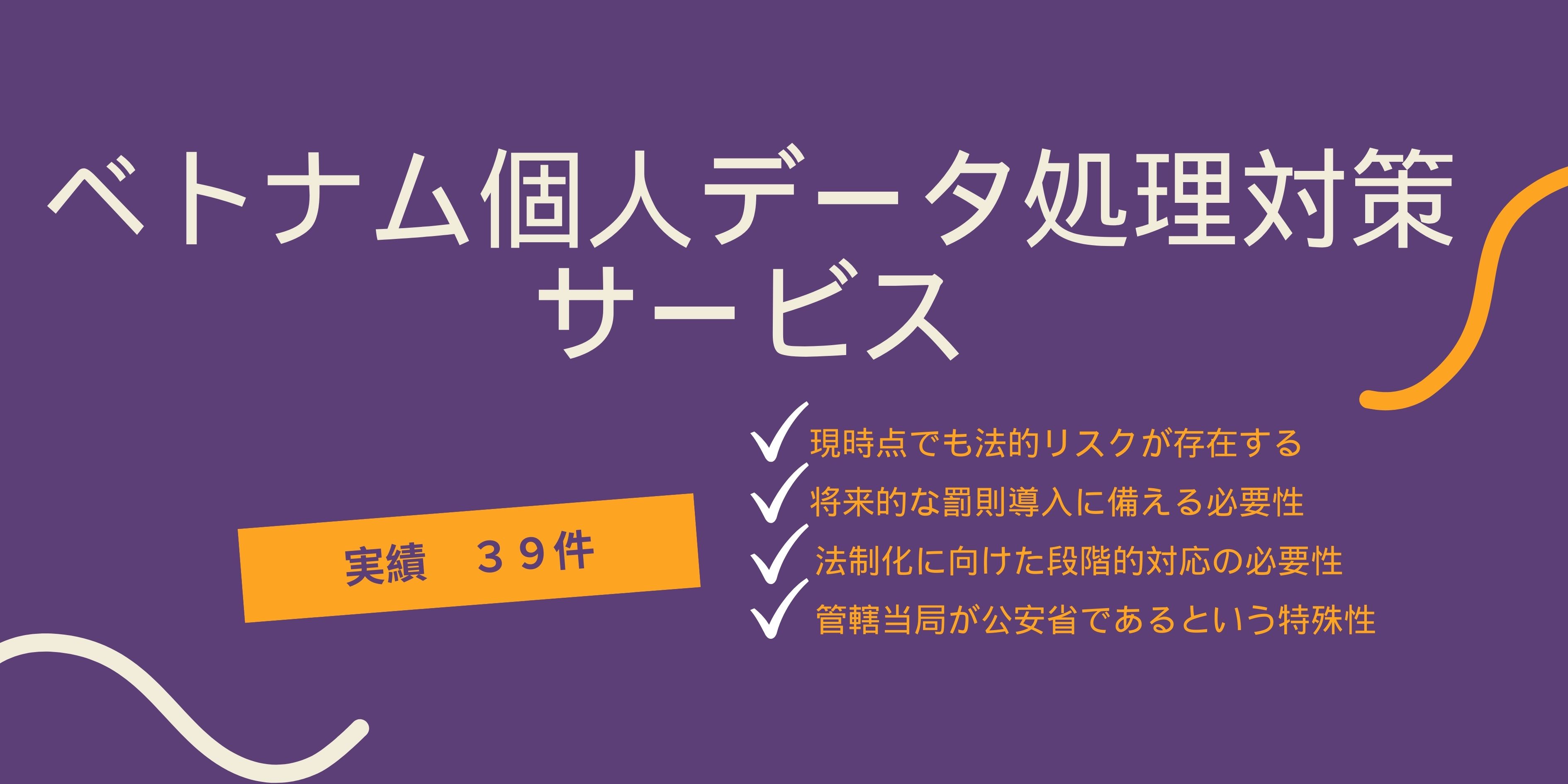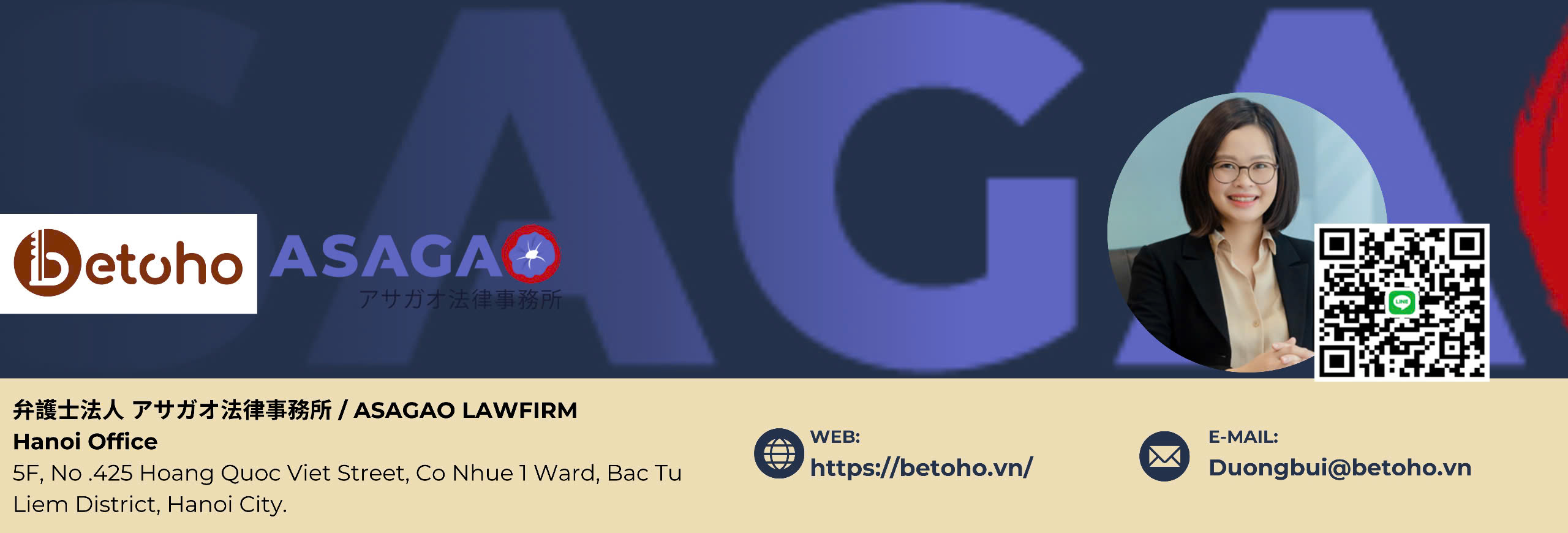|
|
01 - 離婚決断のポイント |
国際離婚を検討する際、離婚という重大な決断は、感情に流されず、冷静かつ慎重に行う必要があります。しかし、実務上、当事者が一時的な感情により離婚を決意し、その後に翻意したり、手続き中に何度も態度を変えたりするケースも少なくありません。
もちろん、夫婦関係が改善される方向への変化は歓迎すべきことです。しかし、離婚と復縁を繰り返すことは、時間的・経済的な負担を増大させる原因にもなります。
このため、弁護士として以下の点を強く推奨いたします。
1.1. 離婚決断前に必ず行うべきこと
- 夫婦関係、子ども、財産問題を含めたあらゆる側面について、冷静に整理・検討した上で決断を下すこと。
- できる限り配偶者との直接対話を試み、双方の認識をすり合わせること。
✅ 難しい場合は、第三者(弁護士など)の介入を活用し、感情的な対立を回避しながら建設的な対話を促す方法も有効です。
1.2. 第三者(弁護士・カウンセラーなど)の活用
- 直接話し合いが困難な場合、弁護士に調整役を依頼することで、冷静な交渉が可能となり、無用な感情的対立を避けられます。
- 弁護士は、法律的な助言だけでなく、現実的な選択肢や解決策も提案できます。
1.3. 家族・友人の意見を参考にする場合
- 夫婦間の対立が単なる誤解や一時的なすれ違いに起因する場合、信頼できる家族や友人の助言が、関係修復のきっかけになることもあります。
- ただし、第三者の意見を過度に重視しすぎず、最終的には自らの意思と責任で決断することが重要です。
|
|
02 - 協議離婚か単独離婚かをどう選ぶか |
国際離婚を考える際、協議離婚(双方合意)と一方離婚(片方からの請求)のどちらを選択するかは、非常に重要な判断ポイントです。
本章では、それぞれの違いや選択時の注意点について解説します。
2.1. 協議離婚を優先すべき理由
離婚に至る事情は様々ですが、できる限り双方で合意して離婚する(協議離婚)ことが、精神的・経済的な負担を最小限に抑える方法です。
- 離婚を申し出る側も、離婚を求められる側も、現実から逃げずに問題に向き合い、冷静に話し合うことが重要です。
- 協議が成立すれば、手続きも迅速かつ円滑に進み、不要なトラブルや追加費用を回避できます。
✅ 合意に至ることで、子どもへの悪影響や、当事者間の感情的な傷を最小限に抑えることもできます。
2.2. 協議が難しい場合の対応
- 相手方が協議に応じない場合、弁護士を通じて状況を説明・説得する方法があります。
- 第三者(弁護士)が介入することで、感情的対立を緩和し、理性的な話し合いの機会を作ることが期待されます。
✅ ただし、実務では、弁護士からの連絡すら無視したり、逆に感情的になる相手も存在します。
2.3. 協議できない場合は一方離婚を選択
相手が協議を拒否し続ける場合、最終的には一方離婚(裁判離婚)を進めるしかありません。
- 裁判所に離婚訴訟を提起し、適切な時期に裁判上の和解(裁判所の和解手続き)を試みることで、改めて合意形成を目指すことが可能です。
- 特に、裁判所主導の和解手続きでは、法的枠組みの中で冷静な協議が行われやすくなります。
|
|
03 - 財産問題への対応 |
国際離婚において、財産問題は夫婦間の深刻な対立を引き起こす主要な要因の一つです。特に、資産の所在や管理方法をめぐる対立は、離婚手続き自体にも大きな影響を与える可能性があります。
3.1. 財産問題が夫婦関係に与える影響
実務上、婚姻破綻の背景には財産問題が関与しているケースが非常に多く見られます。
財産に関するトラブルがエスカレートすると、離婚手続き自体も長期化・複雑化するリスクが高まります。
3.2. 財産主張を行う側が取るべき対応
財産分与を主張する側は、早い段階で証拠収集を徹底することが重要です。
- 財産の取得時期、形態、名義、増減履歴などを証明できる具体的な資料・証拠を収集する。
- 相手方と交渉を行う際に、根拠資料に基づき冷静かつ客観的に説明できるよう準備する。
3.3. 財産争いが激化する場合の選択肢
もし財産問題に関する対立が激化し、離婚自体の進行を妨げる懸念がある場合には、以下のような対応が検討されます。
- 離婚手続きとは別に、財産分与訴訟を単独で提起する。
- 離婚訴訟とは独立した形で財産問題を解決することで、離婚手続き自体を迅速に進めることが可能になります。
✅ 財産分与訴訟を別立てにするかどうかは、ケースバイケースであり、弁護士と相談しながら適切な戦略を立てることが重要です。
|
|
04 - 相手方の不貞行為への対応 |
国際離婚において、配偶者の不貞行為(浮気・不倫)は離婚理由として非常に重大な要素となります。ベトナム法は、一夫一婦制の原則を厳格に保護しており、不貞行為に対して明確な刑事責任も規定しています。
4.1. ベトナム法における不貞行為の禁止
ベトナムの刑法(2015年刑法、2017年改正)第182条は、「一夫一婦制違反罪」について以下のように規定しています。
【刑法第182条】一夫一婦制違反罪
以下の行為を行った者は、戒告、1年以下の拘禁刑または3か月以上1年以下の懲役刑に処される可能性があります。
- 配偶者がいるにもかかわらず、他者と結婚または同棲した場合
- 配偶者のいない者が、既婚者と知りながら結婚または同棲した場合
加えて、以下の条件に該当する場合、処罰対象となります。
- その結果、当該婚姻関係が破綻し離婚に至った場合(第1項a号)
- 過去に行政処分を受けたにもかかわらず再度違反した場合(第1項b号)
✅ 「関係を破綻させ離婚に至らせた」という要件は、最終的に裁判所による離婚判決・決定が確定した場合に成立します。
4.2. 離婚請求権について(民法上の規定)
2014年婚姻家族法第51条は、離婚を請求できる権利者について定めています。
- 夫、妻または両者が離婚を請求できる
- 夫婦の一方が精神障害や家庭内暴力の被害者である場合、
その親、親族も離婚請求が可能 - 妻が妊娠中、出産後、または12か月未満の乳児を育児中の場合、夫からの離婚請求は禁止される
4.3. 不貞行為に直面した場合の対応
配偶者の不貞行為が原因で離婚を検討する場合、
不貞行為の違法性とその重大性について相手方に法的根拠をもって説明することは有効な手段となります。
- **刑事責任(刑法第182条)**が発生する可能性があることを相手に認識させる
- 必要に応じて、証拠を収集し、離婚手続きに備える
- 感情的に対立することなく、冷静かつ戦略的に対応する
✅ 特に国際離婚では、相手が海外に居住している場合も多いため、事前に弁護士による慎重なアドバイスとサポートを受けることが重要です。
|
|
05 - 欠席による離婚手続き |
国際離婚の実務において、欠席による離婚手続き(離婚手続きにおける当事者の不在)は、特に一方または双方が海外に居住している場合に頻繁に発生します。
5.1. 議離婚における欠席審理
- 双方が協議離婚に合意している場合、両当事者が裁判所に対し「欠席審理(審理に出席しないこと)」を申請することが可能です。
- 欠席申請が認められると、裁判所は当事者不在のまま、提出された書類と証拠資料に基づいて審理を進めます。
✅ 欠席審理を活用することで、当事者の負担を軽減し、迅速な解決が図れます。
5.2. 海外在住者の場合の注意点
当事者が海外に居住している場合、通常、裁判所からの通知や文書送達には国際司法共助(司法共助手続き)が必要となり、これにより手続きが大幅に遅延するリスクがあります。
このリスクを回避するため、次の対応が推奨されます。
- 弁護士に対する正式な代理権付与(委任)を行い、弁護士を通じて裁判所とのやり取りを代行してもらう
- 弁護士が裁判所からの送達文書を受領・対応することで、国際共助手続きの手間と時間を大幅に削減できます。
5.3. 海外発行書類の合法化手続き
海外で作成・発行された以下の書類については、
領事認証(合法化)手続きを完了させた上で、提出する必要があります。
- 自認書(自己陳述書、自白書)
- 委任状(弁護士への代理権授与書)
✅ 領事認証が行われていない書類は、ベトナムの裁判所で証拠能力を認められない可能性がありますので注意が必要です。