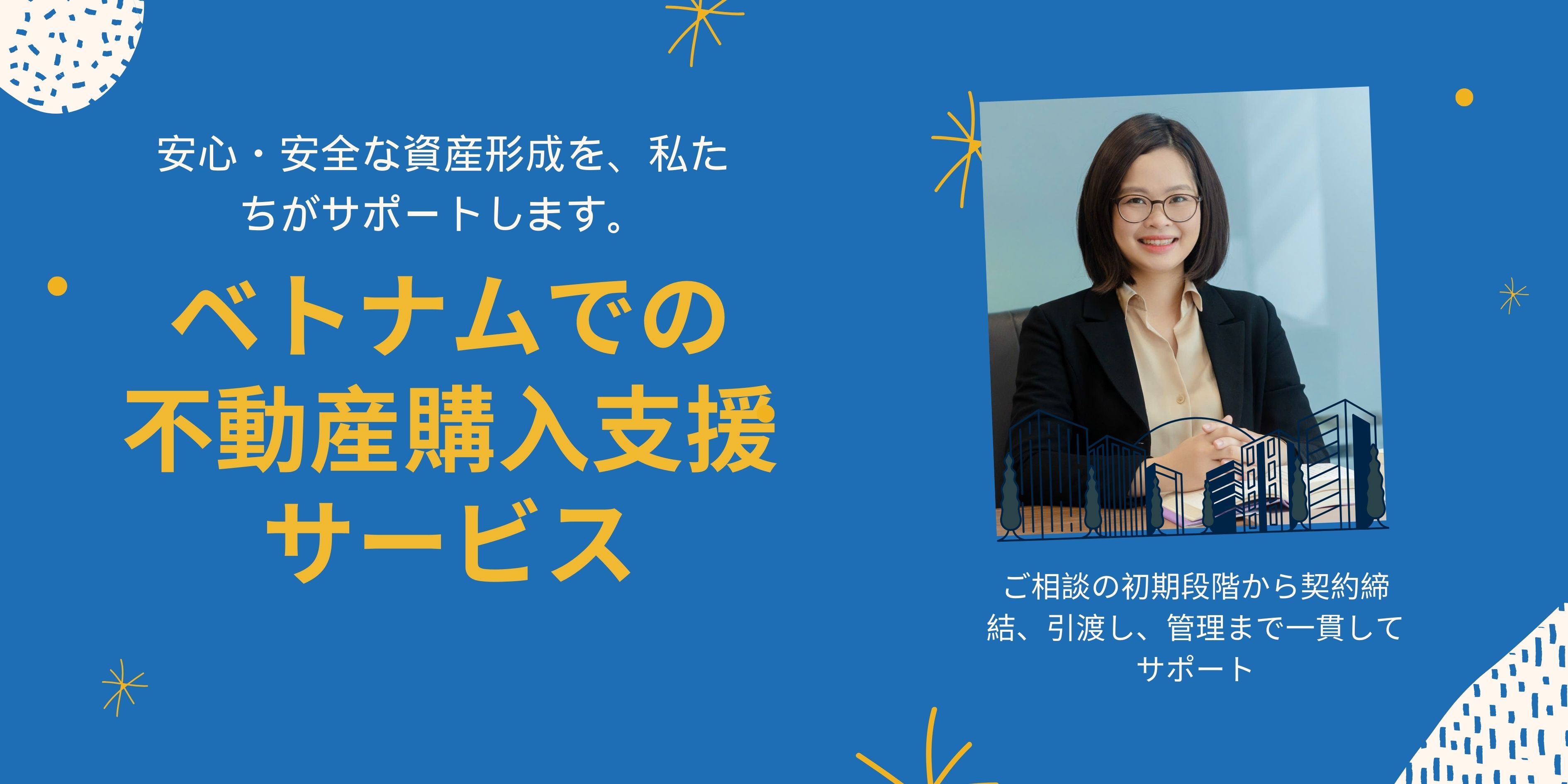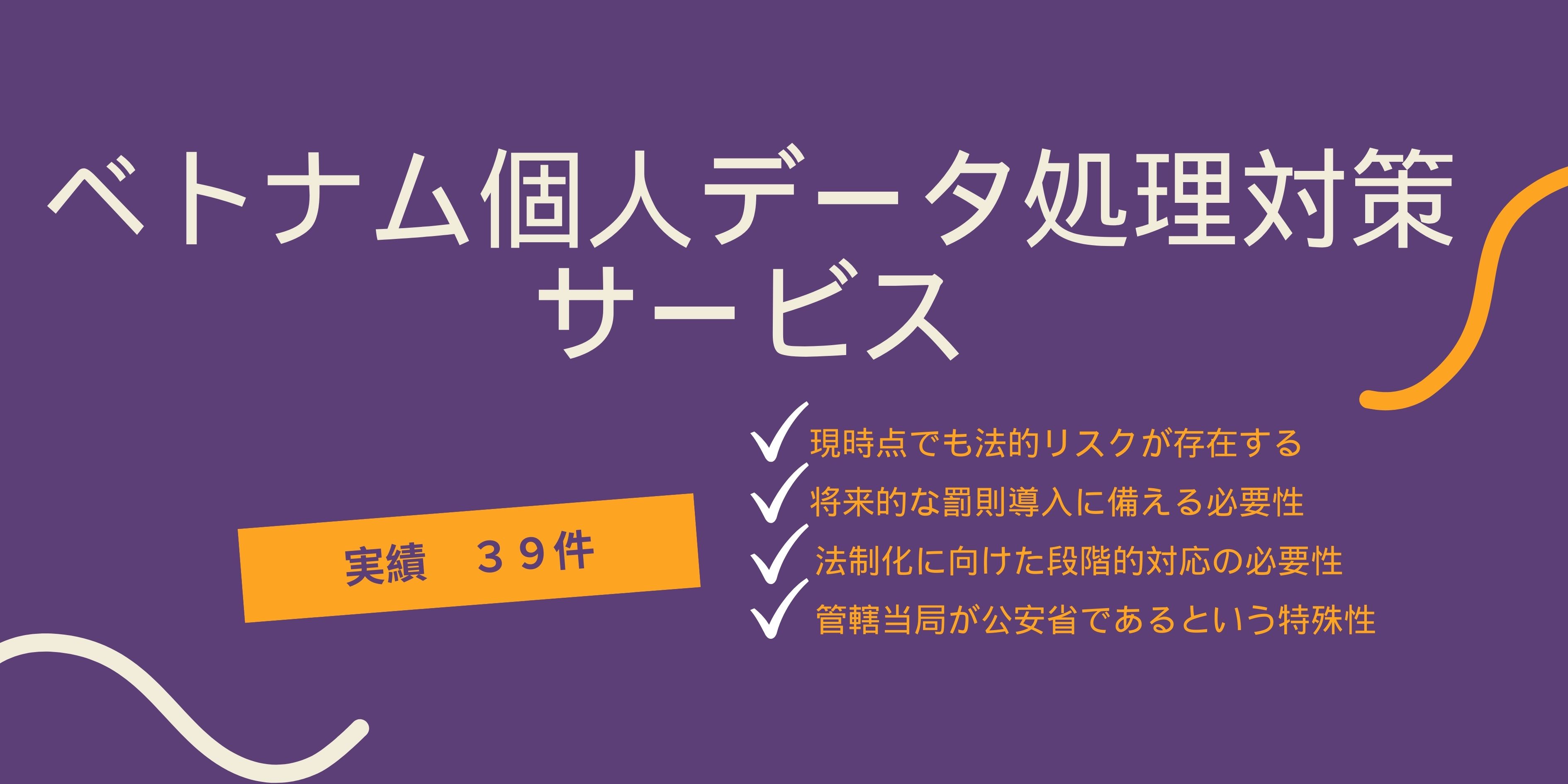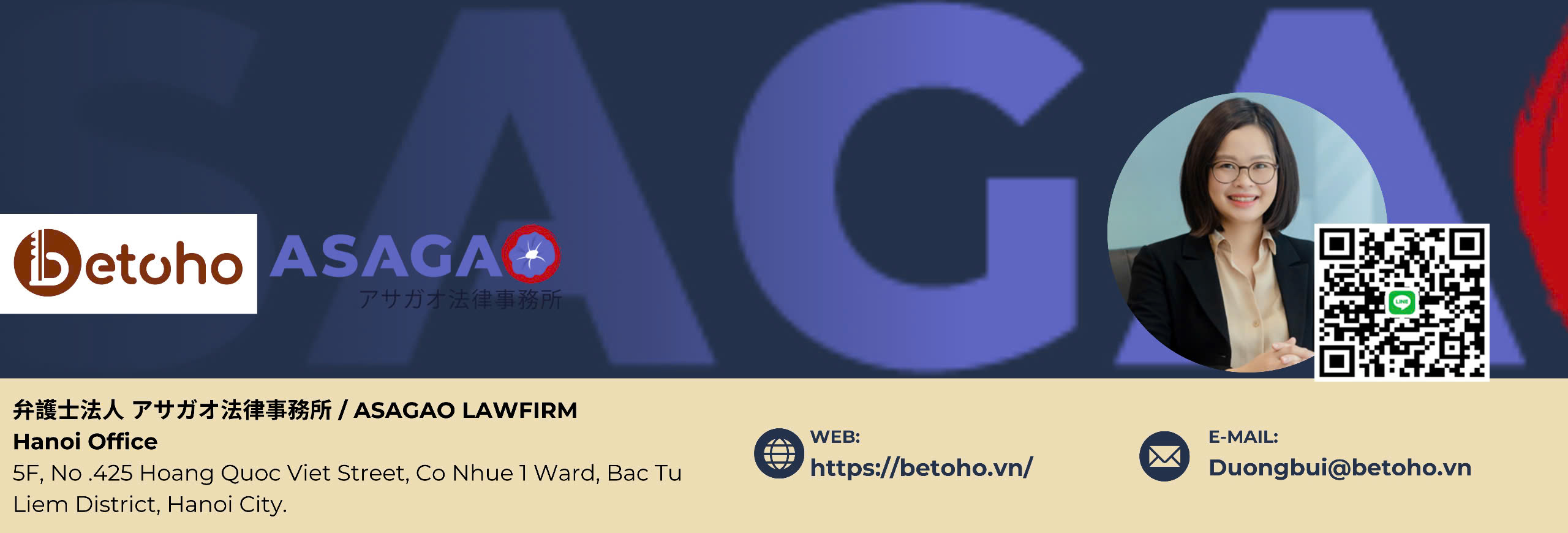|
|
01 - ベトナム不動産事業法2023:成立とその影響分析 |
2023年11月28日、ベトナム国会は「2023年不動産事業法」を正式に可決しました。本法は、ベトナムの不動産取引市場における透明性を高め、長年未解決であった法的課題に対処することを目的としています。
不動産事業法2023は、ベトナムにおける不動産開発、売買、リース、仲介などの商業活動に対して新たな枠組みを提供するものであり、今後の不動産投資環境に大きな影響を与えると期待されています。
本稿では、不動産事業法2023における主要な改正点とその実務的影響について、順を追って詳しく解説します。
|
|
02 - 適用範囲の見直し:不動産取引における明確な分類 |
2023年不動産事業法は、2014年不動産事業法における基本的な適用範囲を概ね維持しつつ、一部の取引類型を明確に適用除外とする規定が新たに導入されました。これにより、どの不動産取引が本法律の規制対象となるかについて、法的判断がより明確化されています。
以下の分類は、不動産取引が不動産法の適用対象か否かを判断するうえでの参考となります。
|
不動産の類型 |
適用対象 |
適用除外(明示的に除外) |
|
公共財産(国家所有資産) |
✖ 対象外 |
● 公共財産として法適用外 |
|
土地使用権(インフラ整備済みで事業目的) |
● 対象 |
– |
|
住宅(既存および将来完成予定) |
● 対象 |
● ベトナム労働総連盟が労働者向けに供給する住宅は除外 |
|
建築物(教育・医療・商業・宿泊・工業など全般)およびその延床面積部分 |
● 対象 |
– |
|
不動産開発プロジェクト(プロジェクト単位の売買) |
● 対象 |
– |
このように、不動産法2023では、公共部門が関与する特定の住宅供給プロジェクトや国家資産等の取引を明示的に除外し、民間の商業取引との区別を法律上明確にしています。
🔹取引の性質による適用除外の規定
2023年不動産事業法では、取引の性質に基づいて適用除外となる不動産取引の範囲が明確に定められました。これは、2014年法に比べて、商業目的外の取引や司法的手続きを通じた不動産の移転について、法律の適用対象から明確に除外することを意図したものです。
具体的には、以下のような取引は不動産事業法2023の適用対象外とされています:
- 裁判所の判決、仲裁判断、または行政機関の決定等に基づいて行われる不動産の譲渡(相続、分割、合併、統合等の法的手続きに基づく所有権の移転を含む)
- 事業目的ではない住宅や建築物の譲渡(個人や団体による非商業目的での建物や床面積の売却)
- 「小規模」に該当する住宅や建築物の売買・賃貸・リース契約
ただし、ここで注目すべき点は、これらの除外規定は「土地使用権の売買」には適用されないという点です。つまり、たとえ取引が小規模であっても、土地使用権の譲渡については不動産事業法の規制対象となるということです。
|
|
03 - 「不動産プロジェクト」の新たな法的定義 |
不動産事業法2023年においては、「不動産プロジェクト」の概念が明文化され、従来よりも包括的かつ具体的に定義されました。新法によれば、不動産プロジェクトとは、「権限ある機関によって法令に基づき承認された、住宅、建築物、またはインフラが整備された土地使用権を事業目的で開発・販売するための建設投資プロジェクト」を指します。
この定義には、以下のような多様な不動産開発プロジェクトが含まれます:
- 住宅建設投資プロジェクト(マンション、戸建て住宅など)
- 都市開発プロジェクト
- 農村住宅地開発プロジェクト
- 教育、医療、スポーツ、文化、オフィス、商業、サービス、観光、宿泊、工業などの特定目的建築物の建設プロジェクト
- 上記機能を複合的に備えた複合用途建築物の建設プロジェクト
- 技術インフラ建設プロジェクト(道路、電力、水道など)
- 工業団地、産業クラスター、ハイテクパークのインフラ整備プロジェクト
|
|
04 - 取引対象となる不動産資産の明確化 |
不動産事業法2023年は、商業取引の対象となる不動産資産の範囲について、従来よりも明確かつ柔軟な規定を導入しました。以下にその主要なポイントを整理します。
✅ 検収済み資産も「完成済み資産」として取引可能
本法では、「完成済みの住宅または建築物」とは、使用目的に応じた検収(検査)を完了し、使用可能な状態となった建物を指します。これは2014年法における「使用開始済み」との定義から一歩踏み込み、引き渡し前であっても検収済みであれば取引可能な資産として認める点が大きな変更です。これにより、開発業者はより早い段階で資産を流動化できる柔軟性を得ることになります。
✅ 土地使用権の範囲は限定的に
不動産事業法2023年では、あらゆる種類の土地使用権の取引を規制対象とする立場から転換し、現在では不動産プロジェクトにおいてインフラ整備済みの土地使用権に限定して、不動産取引の対象としています。これにより、農地や未開発地の不動産ビジネスへの利用は制限され、プロジェクトの合法性と透明性が高まります。
✅ 観光・宿泊・複合機能建築物も対象に
本法はまた、観光施設・宿泊施設・複合機能施設などの特定用途建築物も不動産取引の対象として明文化しています。これは、コンドテル(condotel)やオフィステル(officetel)といった近年注目される形態の不動産開発に対して、一定の法的地位を与える方向性を示すものであり、今後の実務運用における法的安定性の基盤となります。
✅ 建物の床面積部分の取引も合法化
さらに、不動産事業法2023年は、建物内の床面積単位(例:オフィスフロア、小売区画)を取引対象資産として明確に認め、オフィスビルや商業施設における部分売買・賃貸の合法性を確保しています。これにより、実務上頻繁に行われていた床面積単位の契約に法的根拠が与えられ、リスクが大きく軽減されます。
|
|
05 - 不動産取引における情報公開の強化義務 |
不動産事業法2023年では、不動産を市場で取引可能な状態とするための前提条件として、情報公開の義務が大幅に強化されました。これは、取引の透明性と消費者保護の観点から、極めて重要な改正ポイントといえます。
✅ 公開が義務付けられる情報の範囲が拡大
まず、公開対象となる情報および資料の範囲は、従来法に比べて詳細かつ包括的に規定されています。不動産事業者(とりわけプロジェクトの開発主体)は、以下の主要書類を自社の公式ウェブサイト等で公開する義務を負います:
- 投資方針決定の承認書
- 承認済み詳細マスタープラン(1/500規模)
- 土地割当または賃貸に関する決定書
- 建築許可証
このような法的文書の公開により、投資家や購入者はプロジェクトの合法性・信頼性を事前に確認できるようになります。
✅ 政府の公式情報システムへの登録も義務化
加えて、不動産事業者は、自社サイトでの公開に加え、政府が運営する「住宅および不動産市場情報システム」上にも該当情報を登録・公開する義務があります。これにより、中央集権的な監視体制の下、情報の透明性と一元的なアクセスが確保されます。
✅ 情報公開は「取引開始の条件」
さらに、法的に明確にされた点として、情報公開の完了が不動産を正式に販売・賃貸するための条件とされていることが挙げられます。つまり、必要情報を公開していない状態での不動産取引は、法的に認められず、違法性を問われる可能性があります。
|
|
06 - すべての開発事業者に適用される最低自己資本要件 |
不動産事業法2023年では、不動産プロジェクトを通じて事業を行う企業に対して、明確な最低自己資本要件が規定されました。これは、開発事業者の財務的健全性を確保し、プロジェクトの実現可能性を高めることを目的とした措置です。
具体的には、以下のような基準が設けられています:
- 土地使用面積が20ヘクタール未満のプロジェクト:総投資額の**少なくとも20%**の自己資本を確保すること
- 土地使用面積が20ヘクタール以上のプロジェクト:総投資額の**少なくとも15%**の自己資本を確保すること
また、同一企業が複数の不動産プロジェクトを同時に進行している場合には、各プロジェクトごとに上記の自己資本要件を個別に満たす必要があると明記されています。
|
✅ 誤解されうる「厳格な解釈」への注意点✅ |
|
一部の法律専門家では、本規定について「いかなる状況においても、株主または資金提供者が当該プロジェクト会社の自己資本比率を常に20%維持しなければならない」とする、極めて厳格な解釈も存在します。しかしながら、このような理解は、実務的にも合理性に欠けると考えられます。 というのも、たとえプロジェクトが完了し、全ての不動産商品が販売済みとなった後であっても、なお自己資本比率の維持が求められることになり、これは本来の立法趣旨に反する可能性があるためです。 本条文は、プロジェクトを「実行するための最低自己資本要件」に関する規定であり、企業としての信用力を担保する「法定資本(定款資本)」に関するものではありません。したがって、文理解釈と実務的文脈を踏まえた柔軟な適用が求められるといえるでしょう。 |
|
|
07 - 外資系経済組織による不動産事業の明確化 |
不動産事業法2023年は、外国投資資本を有する経済組織(以下、外資系経済組織)の不動産事業に関する権利と範囲を、従来よりも明確に規定しています。
✅ インフラ整備済み土地の事業活用が正式に認められる
新法では、外資系経済組織が不動産プロジェクトを通じて、既にインフラが整備された土地に対し、開発・譲渡・賃貸・再賃貸といった商業活動を行うことが明示的に認められました。これにより、工業団地や技術区などの開発に関与する外国投資家の実務に、法的根拠が与えられた形となります。
現行の不動産事業法(2014年版)では、外資系企業の不動産取引は「住宅および建築物」に限定されており、土地利用権の譲渡・賃貸についての明文化はされていませんでした。もっとも、実際には土地法など他の法令に基づき、既に多くの工業インフラ開発が外国投資家によって行われており、今回の改正は形式的な追認に近いものと解されます。それでも、法的な整合性の確保という観点では大きな意義を持ちます。
✅ 用語の統一:「外資系経済組織」への変更
さらに、今回の法改正では、用語の使用にも見直しが行われ、「外国投資資本を有する経済組織という表現が一貫して使用されるようになりました。これは、2020年投資法における定義と整合性を持たせるための措置と考えられます。
一方、従来の2014年法では、「外国投資資本を有する企業」という用語が使われていたものの、その法的定義が不明確であったため、実務上の混乱を招く一因となっていました。
|
|
08 - 建物内の床面積の譲渡・リースバックが正式に認められる |
不動産事業法2023年は、現行の土地法のアプローチに基づき、建築物における床面積の個別取引を正式に認める方向へと踏み出しました。一定の条件を満たす限り、建築物の一部区画、すなわち床面積単位での譲渡またはリースバック(賃貸+買取)契約が可能となります。
法令上の条件としては、譲渡対象の床面積が存在する建築物は、以下のような土地使用権に基づいて建設されたものである必要があります。
- 国家より有償で土地使用権が交付された場合(使用料一括払い)
- または、一括で支払う形式で土地を賃貸された場合(賃貸料一括払い)
この新たな規定は、市場実務に適応しやすくなる一方で、以下のような問題も懸念されています。
- 不動産事業法2023年は、改正土地法との調整が十分に反映されていない状況です。新しい土地法では、国家が土地を一括賃貸するケースは大幅に制限される見通しであり、現実には多くの商業・サービス用地が「年払い」での土地賃貸契約に該当します。したがって、現行の規定では多くの開発プロジェクトが対象外となるリスクがあります。
- もっとも、不動産事業法2023年では、売買契約において土地に関する財務義務(地代・使用料など)を明確に取り決めることを義務付けており、支払い方式(年払い・一括払い)そのものは重視されない可能性もあります。
|
|
09 - 行政違反がある場合、不動産の取引が一時的に制限される |
不動産事業法2023年 第19条第1項p号の規定によれば、不動産開発事業者が投資法、建設法、土地法、住宅法、不動産取引法、または税法に違反し、行政処分を受けている場合、当該事業者は処分が完了するまで、住宅または建築物の売買・賃貸・リースバック契約を締結することができません。
この規定は、次のような違反に該当する事業者を対象とします:
- 投資活動における許認可の不備
- 建築基準の違反または無許可施工
- 土地利用に関する法令違反
- 不動産事業ライセンスに関する義務違反
- 税務申告・納付に関する不備
これにより、行政処分を受けている最中の不動産が市場に流通することを防止し、消費者保護および不動産市場の信頼性を担保することが狙いとされています。取引を再開するには、当該事業者が行政処分に基づく是正措置をすべて完了した上で、正式に履行済みと認められる必要があります。
この制度は、不正行為を抑止すると同時に、不動産取引の透明性と安全性を制度的に保証する枠組みと位置付けられています。