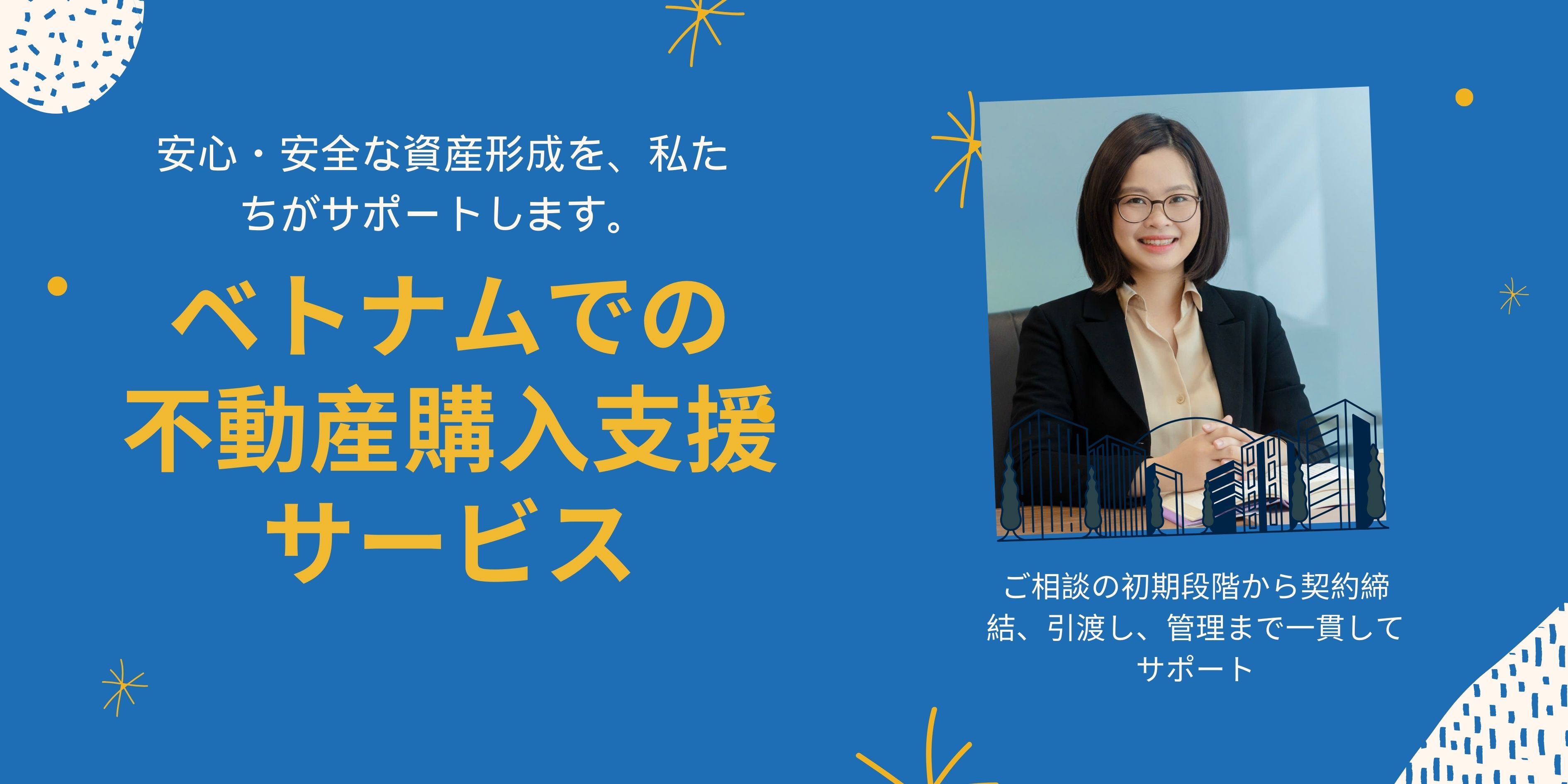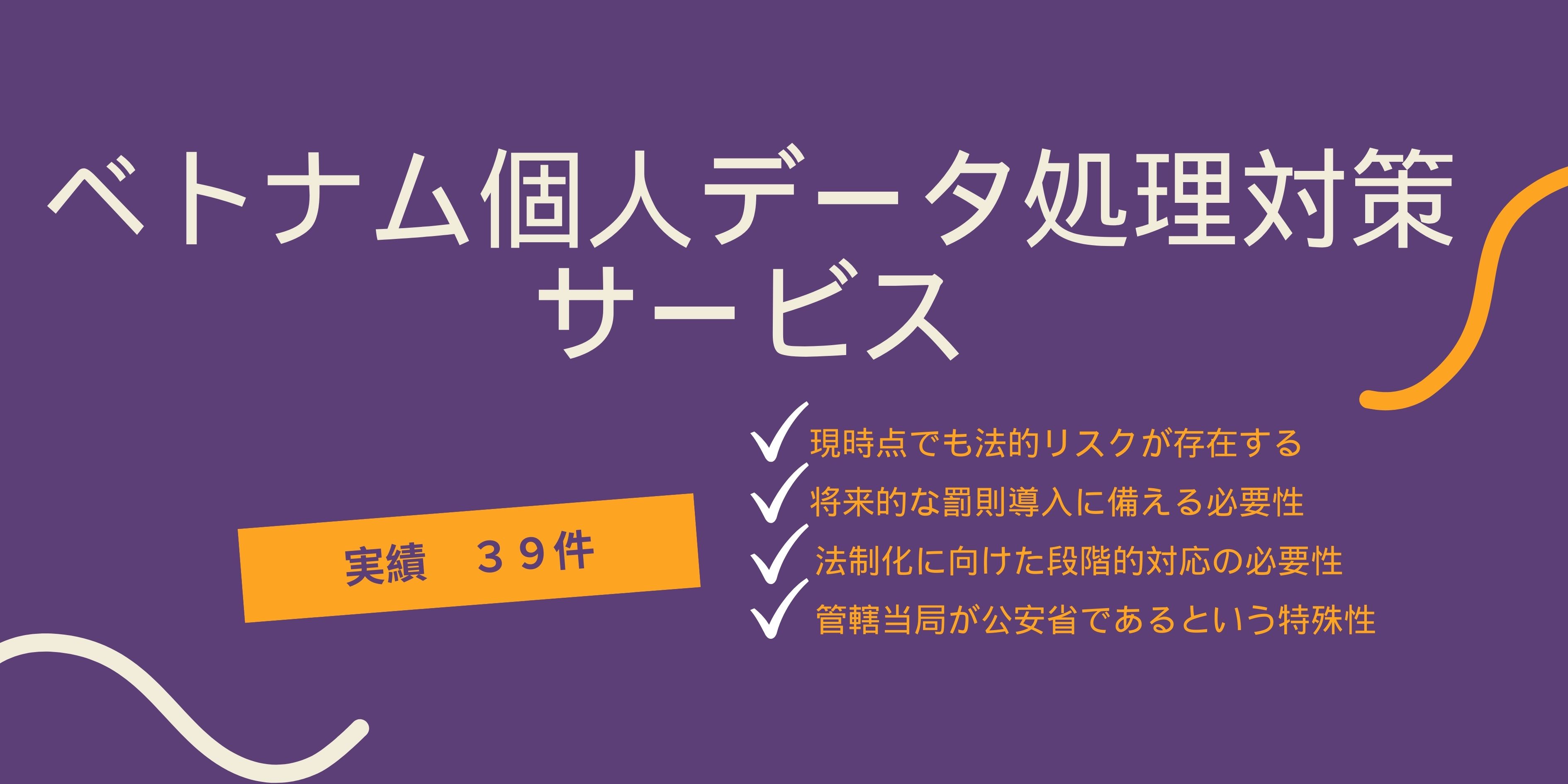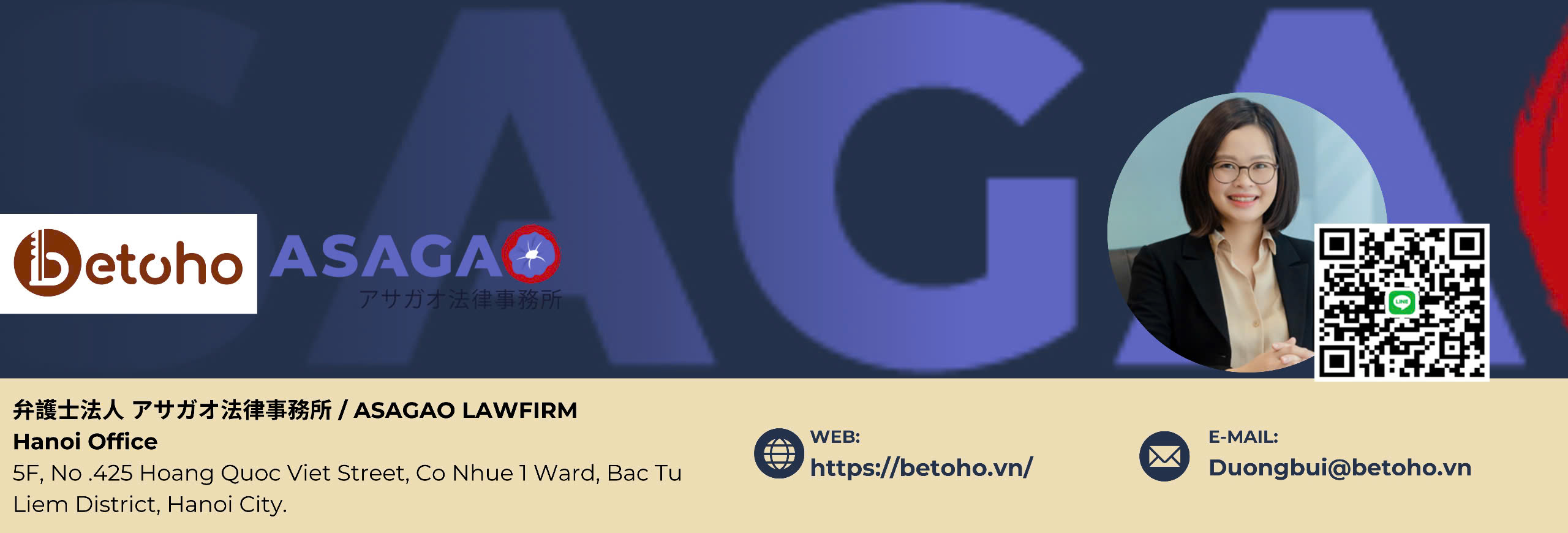|
|
01 - 事案の概要 |
|
XXX社は、ベトナムに所在するYYY社(以下「破産法人」といいます)に対し、一定額の売掛債権を有しておりましたが、2024年1月時点で、当該破産法人がハノイ市人民裁判所に対して破産手続を申立てたとの通知を受けました。 XXX社は債権者として、今後の破産手続に参加し、債権回収を試みるか、あるいは事実上債権放棄するかについて、経済的合理性および法的観点からの検討を求めました。 |
|
|
02 - ベトナム弁護士による法的助言 |
▶ 法的論点①:ベトナムにおける破産手続の概要と債権回収の見込み?
- ベトナムでは、破産法(2014年改正)に基づき、裁判所による破産開始決定 → 債権者集会 → 財産清算・分配という流れで破産手続が進行します。
- ただし、実務上は制度運用が未成熟であり、手続完了まで2年以上かかることが通例とされています。
- 本件では、破産法人自らが申立てを行っており、手続が異常に迅速であること、また資産隠匿・財産移転の疑いがあることから、債権回収の可能性は極めて低いと推察されます。
● 債権回収の阻害要因(実務的リスク):
- 開始決定前に第三者への資産移転の可能性
- 財産管理人の能力・中立性に不安
- 管轄裁判所による債権者保護意識の欠如
- 他の債権者(銀行等)の担保付債権が多数存在
▶ 法的論点②:分配順位とXXX社の立場
破産法において、弁済順位は以下のとおり定められています。
|
順位 |
弁済対象 |
|
① |
担保付債権者(抵当権・質権保有者) |
|
② |
破産手続に係る費用 |
|
③ |
従業員給与・社会保険料等 |
|
④ |
事業維持費用(最低限) |
|
⑤ |
国への税金等の支払 |
|
⑥ |
一般債権者(XXX社はこの区分) |
本件では、既に担保付債権者が複数存在し、債権者の総数も100社以上であることから、一般債権者であるXXX社が分配を受けられる可能性は極めて低いと評価されます。
▶ 法的論点③:債権回収までの期間と実務負担
- 清算対象の財産が債権である場合、回収手続は最大2年に及ぶことが想定されます。
- 仮にXXX社が破産手続に参加した場合でも、弁済を得られるか不確実であり、手続参加のための人的・時間的・費用的コストが高いことが懸念されます。
▶ 法的論点④:債権放棄という選択肢
- ベトナム破産法では、裁判所からの「債権証明書類の提出要請」に対して無反応であった場合、事実上の債権放棄とみなされ、以後の手続には関与できなくなります。
- 一方で、手続に参加した場合は、一定の監視権・異議申立権を有することとなります。
|
選択肢 |
要提出書類 |
権利内容 |
負担 |
|
債権手続に参加 |
債権証明資料 |
債権者集会出席・配当請求等 |
高い |
|
債権放棄 |
提出不要 |
なし(放棄) |
極めて軽い |
したがって
- 債権放棄の方向で検討することが、経済合理性の面から最も妥当と考えられます。
- ただし、企業の会計処理上の影響(貸倒損失計上等)や、他の債権者との関係整理については、社内手続との連携が必要です。
|
◆結論と今後の対応指針◆ XXX社が本件破産手続において債権回収を行うことは、法的可能性としては存在するものの、実務的・経済的合理性が著しく低いと判断されます。 ✅推奨方針
|