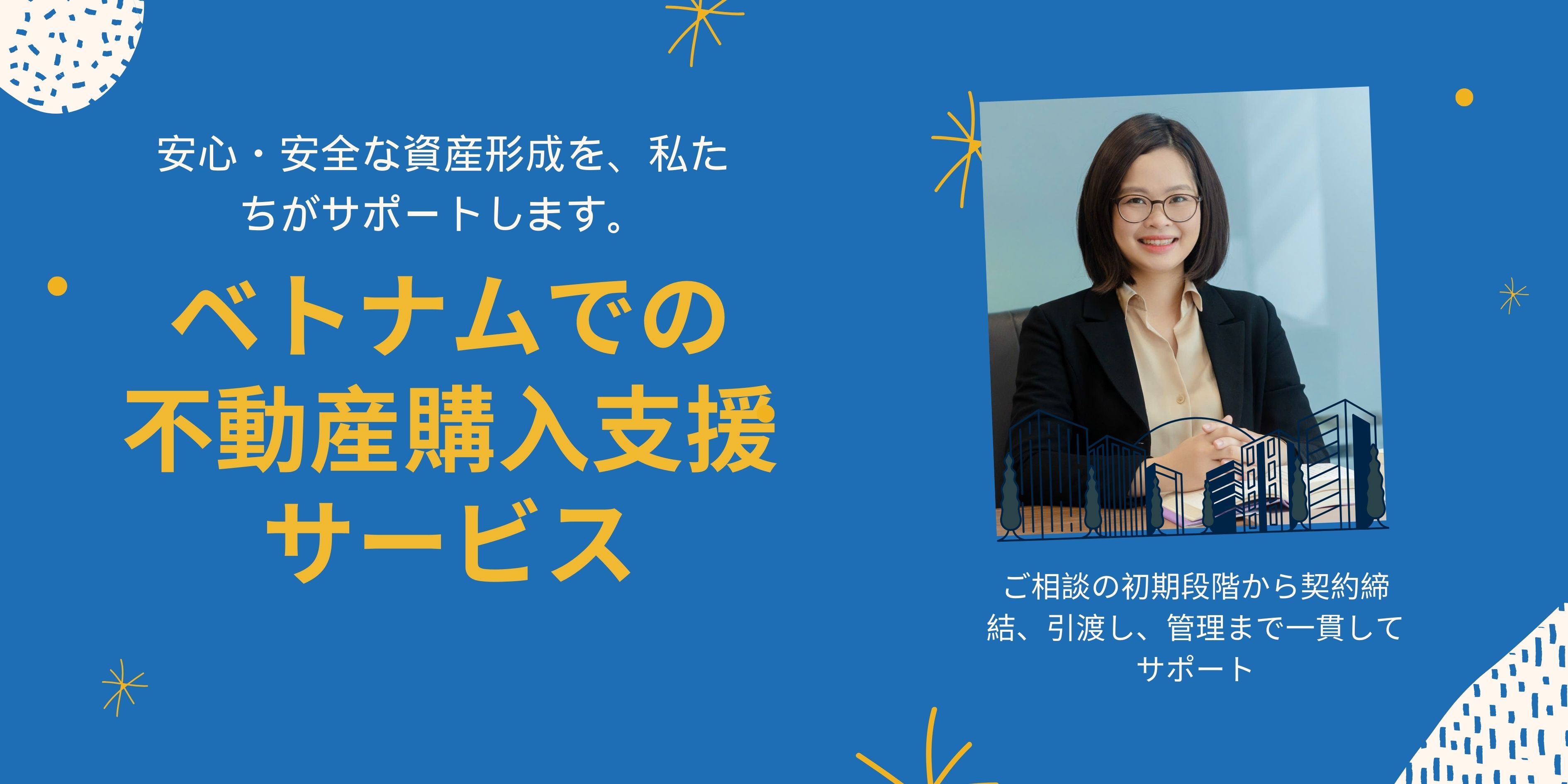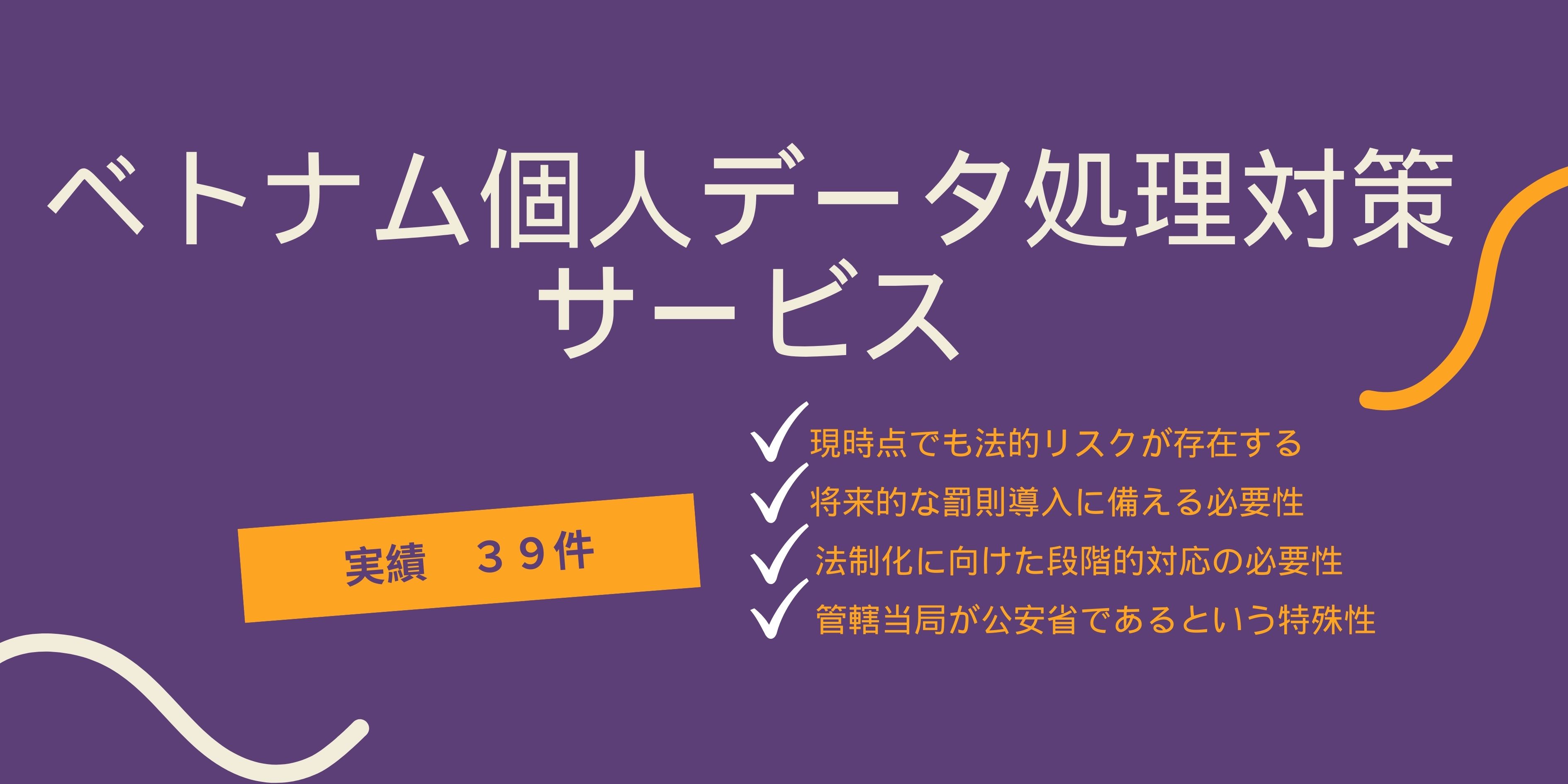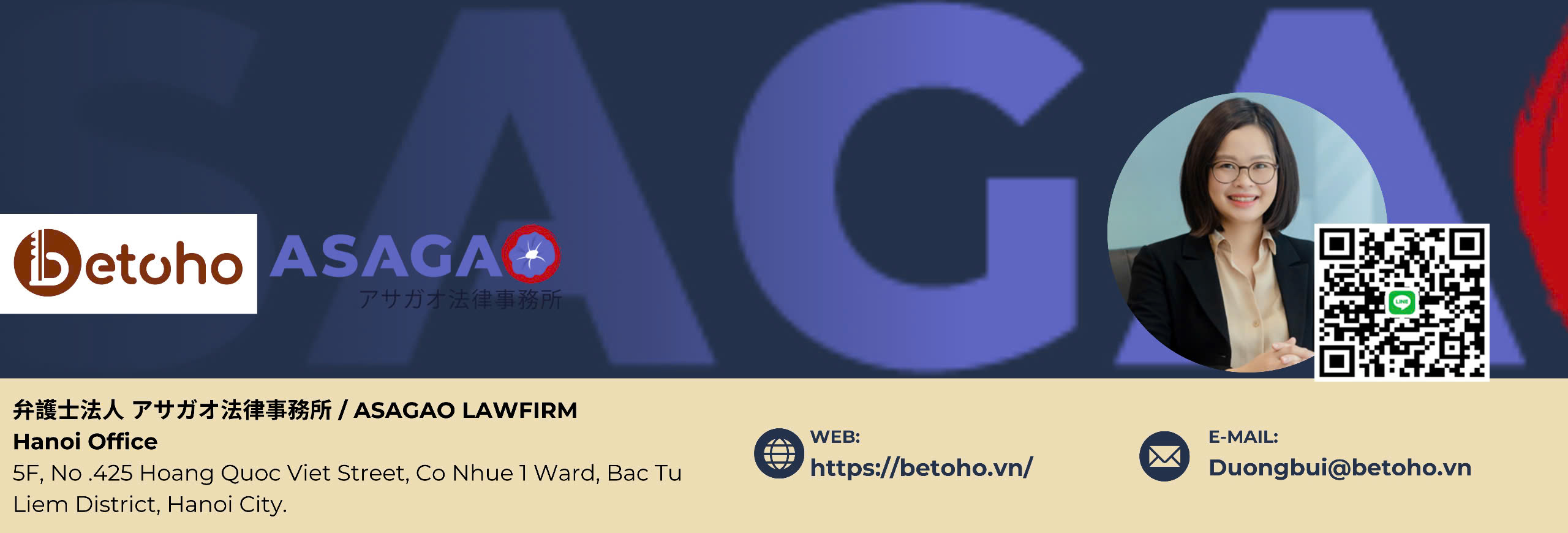ベトナムでは、いくつかの特定業種(例:映画上映サービス、陸上輸送サービスなど)において、外国投資家は出資比率に上限が設定された形で、合弁会社または事業協力契約(Business Cooperation Contract/以下「BCC」)を通じて投資することが可能です。
しかし実務上、「この出資比率制限が合弁会社のみに適用されるのか、それともBCC形態での投資にも適用されるのか」は明確にされておらず、解釈と運用に差異があるため、本稿ではその問題を整理・分析します。
|
|
01 - WTO約束表における出資比率制限とその記述 |
ベトナムがWTO加盟時に提出したサービス分野の約束表では、外国投資家の市場アクセスに関する制限の一つとして、合弁会社における出資比率の上限(例:49%、51%など)が明記されています。一部業種では、投資形態として「合弁会社またはBCC」のいずれかを許可している旨が記載されています。
このような記載から、「BCCにも同様の出資比率制限が適用される」と解釈する余地があるものの、WTO約束表において「出資比率(equity capital)」という概念自体は法人形態に紐づいたものであり、法人格を持たないBCCには原則適用されないという見方もあります。
|
|
02 - BCCにおける資金拠出と出資の違い |
BCC契約では、各当事者の「出資比率」に相当する概念として、「出資割合」「利益分配割合」などを設定しますが、BCC自体は新たな法人を設立するものではなく、各当事者が独立した主体として契約に基づいて協働する形式です。そのため、合弁会社に適用される「出資比率の上限」という概念をBCCに機械的に適用することは、制度設計上、論理的な整合性を欠きます。
|
|
03 - 投資法(2020年版)の視点からの分析 |
ベトナムの2020年投資法において、外国人投資家に対する「市場アクセス条件」として、出資比率の制限は「法人(組織)」に対するものとして位置付けられていることが明確になっています(第9条参照)。
一方、BCCは法人格を持たない「契約ベースの投資形態」であるため、理論的にはこの制限の対象から除外されると解釈できます。これは、法的立場として「出資比率制限=法人に対する制限」と解釈していることを裏付けています。
|
|
04 - 実務上の取扱いと政府見解 |
実務上、関連当局からの非公式な見解として「出資比率制限は原則として合弁会社にのみ適用され、BCCには直接適用されない」という説明がなされるケースが散見されます。
また、特定の外国人投資家がBCCを通じて参入するケースにおいて、明示的に出資比率制限が問題とされた例は少なく、現実には投資家の拠出割合や利益分配比率が柔軟に設定されているのが実態です。
|
|
05 - 法的・実務的留意点 |
とはいえ、以下の点に注意する必要があります:
- 一部の専門業種(例:電気通信、映画上映など)では、関連法令やライセンス取得要件において、実質的な外国支配の回避を目的とした制限が別途課される可能性があります。
- BCCといいながらも、外国側の実質的支配が明らかな場合には、当局から指摘・修正要求がなされるリスクも存在します。
|
➡結論 現時点での法令・実務運用を総合的に勘案すると、外国人出資比率の上限は原則として法人(合弁会社)に対して適用されるものであり、BCCには直接適用されないと解されます。 ただし、特定分野や具体的スキームに応じて、出資比率と実質的影響力とのバランスについて個別に審査される可能性もあるため、事前に法的リスクを精査し、慎重に契約構成を検討することが重要です。 そのため、BCC契約を作成する際に、必ず弁護士にご相談しながら進めるべきです。 |